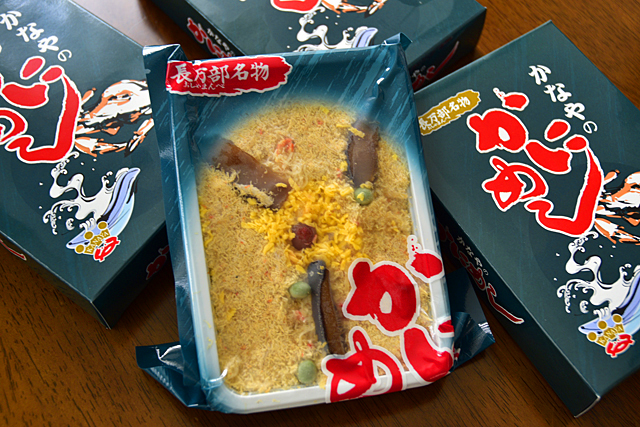海に最も近い駅・千綿駅と大村湾に沈む夕日

長崎空港がある大村から、JR大村線でも国道34号でも、20分弱で千綿駅に着きます。この駅については、「旅先案内」の記事( 海の見える千綿駅とそのぎ茶で有名な町 )にも書いていますので、暖簾分けしたこちらは再登場となります。 千綿は、もともと長崎街道25宿の松原宿(大村市)と彼杵宿(東彼杵町)の間宿(あいのしゅく)だった所です。宿駅として商工業が栄え、宿場であった約400mの街道筋には江戸時代の住宅も残り、長崎県の景観資産に指定されています。 1928(昭和3)年開業の千綿駅は、海の見える駅として知られ、2014(平成26)年には青春18きっぷのポスターになりました。そのキャッチは「18時16分 小さな改札をくぐった。大きな夕日が迎えてくれた。」でした。「海とホームが日本一近い駅」とも言われる千綿駅。遮るものなく見られる、大村湾に沈む夕日は、確かに格別です。 東彼杵町役場商工観光係がYoutubeにアップしていた動画(オリジナル→ https://www.youtube.com/watch?v=bf_v_zV8l6Y )を編集して、一部早送りにしたので、埋め込んでおきます。ちなみに、動画の説明には、「列車が傾いて停まる駅としては日本一美しい夕景だと長距離トラックドライバーさんのお墨付きです。映画ロケとタモリ倶楽部様お待ちしています。ちなみに各停とイベント列車しか停まりません」とありました。「列車が傾いて停まる駅としては」というのが気になりますし、長距離トラックドライバーさんって誰よ、とツッコミたくなりますが、青春18きっぷのポスターより夕日が際立っているので、良かったらチラ見してください。 で、「旅先案内」の記事にも書きましたが、現在の駅舎は、開業当時の駅をイメージして、1993(平成5)年に建て替えられたものです。ホームは、大村湾の海岸線に沿って設置されているため、カーブしており、そのため「列車が傾いて停まる駅」ってことになるわけです。 駅は、私が行った当時は無人駅で、何もありませんでしたが、16年から、東彼杵町のまちおこしグループ「長咲プロジェクト協議会」が管理業務を担当。現在は、佐世保から移住してきた湯下龍之介さん、香織さんご夫婦が、駅舎の業務管理責任者を兼ねて、「千綿食堂」という名の小さな食堂を運営しています。